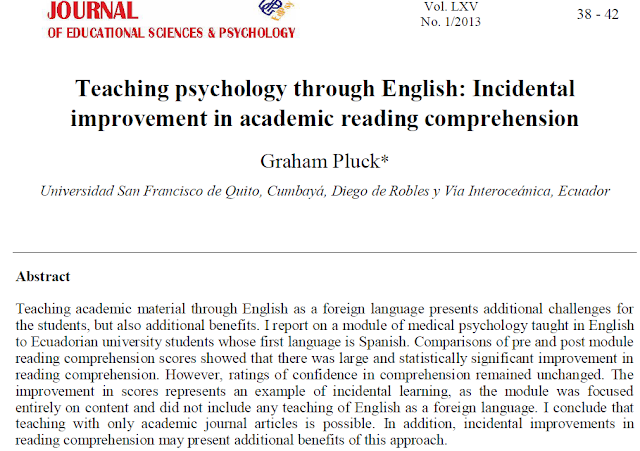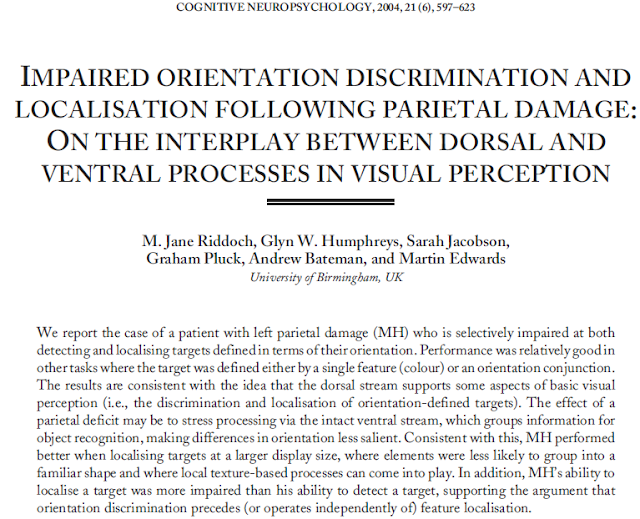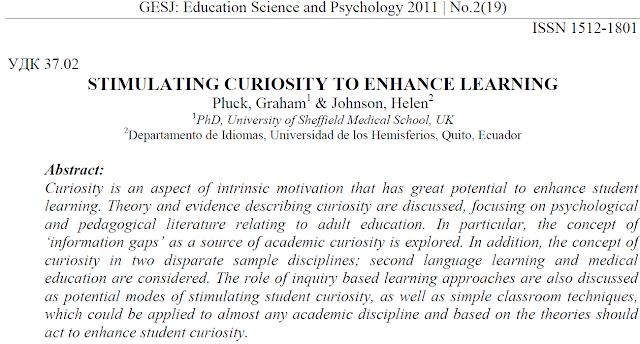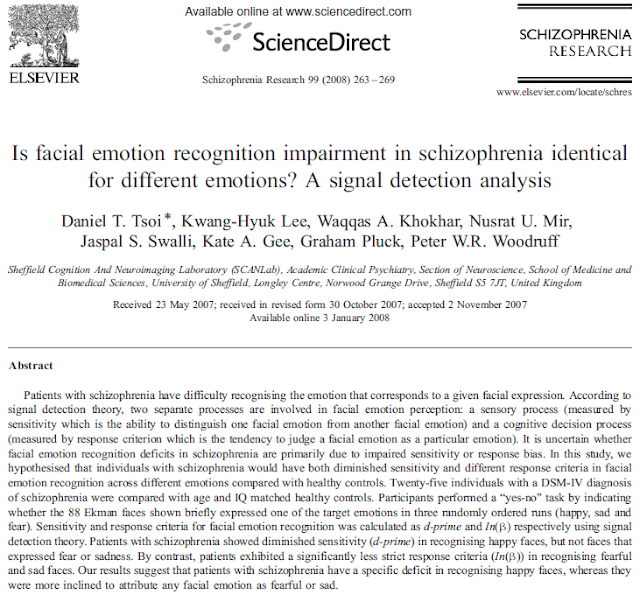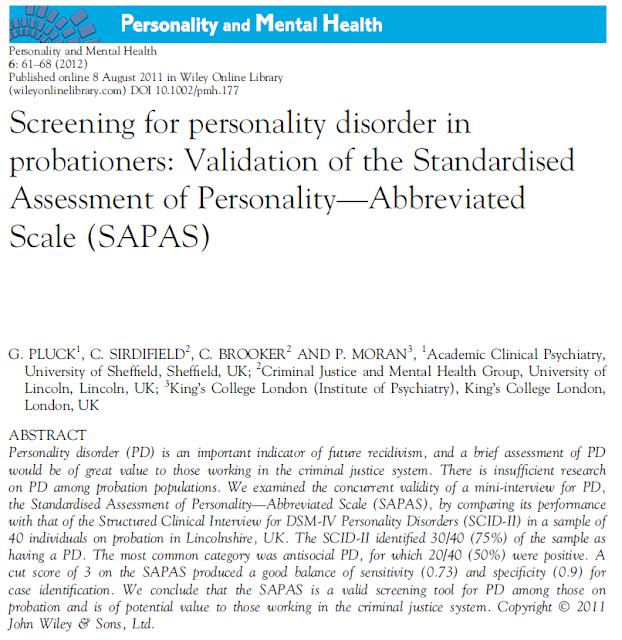外国語としての英語で、学術的な分野を指導することは、学生にとっては付加的な努力を伴うかもしれないが、付加的な利益をももたらすことがある。私は、医学心理学のモジュールに則って、スペイン語が第一言語であるエクアドルの学生に教えたときの、結果を報告する。モジュールの朗読スコアは朗読前後で比較すると、読解力において大きな改善が見られた。しかし、読解後の理解度の自信に変化はなかった。スコアの改善は偶発的な学びの向上を表す、なぜならモジュールは英語の学習を意図する内容は含んでおらず、完全に学術内容重視のものであったからだ。私は学術誌のみを利用した指導は可能だと結論付ける。加えて、このアプローチによって読解力以外の分野も向上する可能性がある。
Pluck G (2013). Teaching psychology through English: Incidental improvement in academic reading comprehension. Journal of Education Sciences and Psychology, 3 (LXV), 38-42.